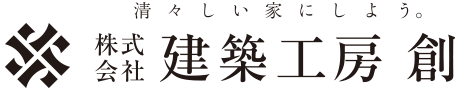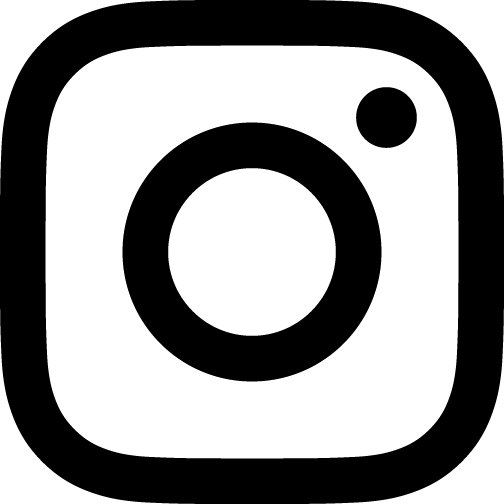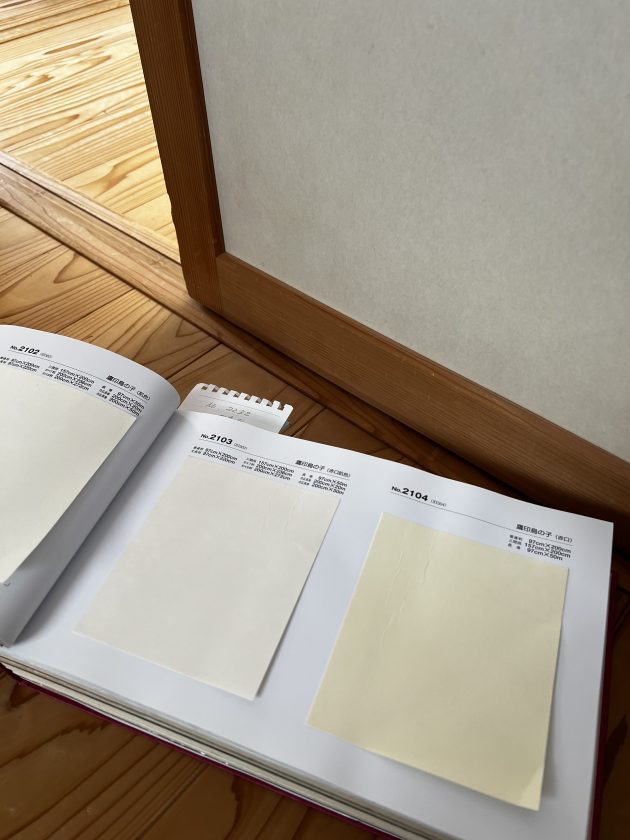沓脱石を創る。
2025年07月27日
民家再生 秋保の家より。
現場では先週より基礎工事の掘削の際に土中より掘りだされた大きな秋保石を高圧洗浄機できれいに洗い流して、形を整えながら大切に家の一部として生まれかわり 「沓脱石」として土間と板の間の間に使うことにしました。
本来「沓脱石」は縁側や玄関などに置かれ踏み台にするための石のことで履物を脱ぐために置かれていました。
古来より日本人は家の中を神聖な場所として据えているため大地には様々な穢れ(けがれ)があると考えられ、この穢れを家の中に持ち込まないように玄関で履物を脱ぐ考え方が弥生時代にはあったとも書かれています。
現場写真の秋保石はまだ施工途中で一段目の据付が完了したところです。更にもう一段、組んでいく予定です。
●↷ 写真は掘削中に掘りあげられた秋保石。

●↷ 洗浄し整えられた秋保石を「沓脱石」として生まれかわります。一段目の施工中の様子。


posted by しん at 11:20 PM