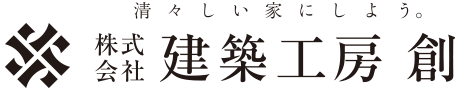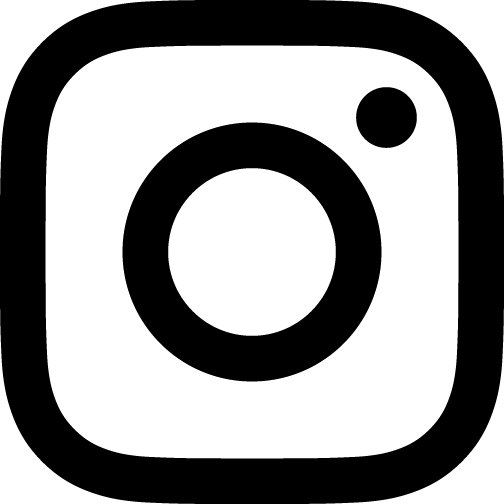基礎工事、開始しました!
2024年10月13日
民家再生 秋保の家より。
現場では木工事と並行して基礎工事を開始しました!
まずは床下からでてきた石を集積して搬出する作業です。でてきました秋保石は後からきれいに洗浄して汚れを落として再び現場内に運び入れて二度目の役割をお願いする予定です。
(秋保石のその後は納めたのちにご報告させていただきます。)
外周部の掘削は建物が不安定な状態でもあるので特に慎重にそしてときに重機オペさんのスコップ作業で丁寧に形を創っていきます。
休みあけも安全に作業を進めていきましょう!ご安全に!
よろしくお願いします!

posted by しん at 10:15 PM